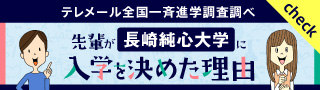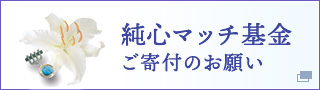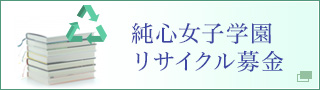福祉・心理学科では、毎年「児童虐待防止推進月間」である11月に行われる「学生によるオレンジリボン運動」に参加しています。児童虐待について多くの方に知ってもらい、児童虐待を少しでもなくすことにつながるよう、本学は長崎県こども家庭課のご協力のもとに活動を実施しています。
「オレンジリボン運動」とは、子ども虐待防止のシンボルとして、オレンジリボンを広めることで子どもの虐待をなくすことを呼びかける市民活動です。オレンジの色は、里親家庭で育った子どもたちが「子どもたちの明るい未来を示す色」として選び、その胸の中に、オレンジフルーツのような明るさと暖かさを感じたいという思いがあったのではないかといわれています。(認定特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワークHP より)
事前学習会として、10月にこども家庭課職員と児童養護施設職員の方々より、児童虐待の現状の話を伺う講義を行うとともに、街頭で配布するためのオレンジリボンを作成しました。
そして、11月9日(土)に長崎駅前で「オレンジリボン運動」を行いました。
活動当日は、長崎県こども家庭課の職員の方々と一緒に、児童虐待に関するポスターを掲示するとともに、自分たちで作成したオレンジリボンや児童相談所全国共通ダイヤル(189=イチハヤク)が明記されたポケットティッシュやチラシを市民の皆さまに配布し、児童虐待防止の推進を呼びかけました。
活動当日は、長崎がんばらんば隊の“がんばくん”“らんばちゃん”も応援に来てくれました。
オレンジリボンに参加した学生の感想
- オレンジリボン運動を通して、足を止めて話を聞いてくれたり、興味を持ってくれたりする方々は多く、児童虐待や育児放棄などは多くの人の関心がある問題なのだと感じた。
私は、今回の活動をするまではオレンジリボン運動という言葉を知らなかったし、内容についても想像もできないほどだった。だが、今回初めて活動をしてみて、児童虐待や育児放棄の問題についてより興味が深まり、活動をした後はより深く知りたいと感じた。そのため、児童虐待について友達と意見を出してみたり、政策について話したりと、実際にオレンジリボン運動をしてみることで今までよりも「知りたい」という感情が大きくなったように感じた。 - 私たちがオレンジリボン運動をしたことにより、地域の人々に日々ニュースになっている児童虐待が社会問題になっていることを改めて感じていただけたら良いと思った。このオレンジリボン運動を通して、私自身以前よりも児童虐待について考えるようになり、なぜ減少しないのか、本当に親だけが悪いのか、など深く考えられるようになったことや街の人と話すことで自分もまだ児童虐待について知らないことが多いため、勉強の必要性を感じた。オレンジリボン運動に参加して良かったと思った。
- 今回のオレンジリボン活動を機に少しでも多くの人が、児童虐待防止について関心を持ってくれたら良いと思いました。年々児童虐待が全国で増え続ける中で、このような呼びかけが少しでも心に残ったら、少しずつでも減ると思うし、防止にもつながると思いました。講義でオレンジリボンの話があったことから、この活動の意味を知ることができたので、地域でどのような活動が実施されているのかをもっと知りたいと思いました。今回ボランティアとして活動に参加させていただいて、とても貴重な体験になり、地域での活動について知ることができたのでとても良かったです。
- 私はオレンジリボン活動を通して、リボンを渡しても何の活動かと聞かれることが多く、声掛けに工夫が必要だと思いました。また、配布物を受け取ってもらえるとうれしかったです。活動により会話が始まることもあり、あたたかい地域との関わりを感じることができ、子供のための活動に貢献できたのではないかと思いました。とても大切な活動に参加させていただき、嬉しかったです。
(オレンジリボン運動担当 大杉・鹿山・岡田)