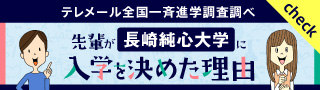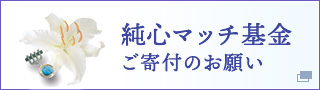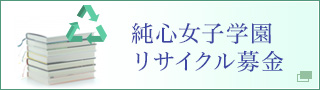「音楽科教育法」の授業で、小学校3年生の対象を想定した模擬授業を行いました。
「音楽科教育法」模擬授業の様子
めあてを児童とつくる場面
めあてを児童とつくるのは、学生にとって難しいですが、頑張っています。
- 前回の記事:パート1「単調を初めて学ぶ」はこちら
授業後の授業者の感想(抜粋)
長調の説明を音階だけにとどめず、これまでに扱った曲に結びつければ、より児童 にとって身近で理解しやすいと感じた。
サミングや息の強さについては、まず児童に吹かせ て「なんか変だな」と気づかせ、その上でどうしたらよいか考えさせる手立てが重要だということを学んだ。自分自身で違和感に気づくことで、そこからどうしたら良いのかと考える きっかけにもなるため、気づかせる手立てもこれから大切にしていきたいと思った。
高学年では、児童自身の気づきや試行錯誤を大切にし、自分で課題を乗り越える力を育て ることがこれから6年生、中学生と続いていく段階で重要になってくると改めて感じた。音 楽は学級づくりにも繋がってくることを学んだため、学年ごとに様々な工夫が必要である と思った。学校や、学年、クラスの実態に合わせた授業づくりが非常に大切になると思う。