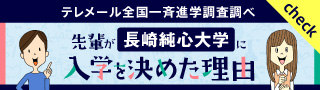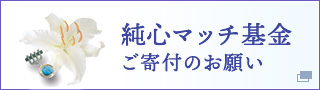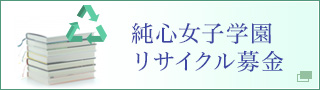令和8年度長崎県公立学校教員採用選考試験 (中学校・高等学校) において、文化コミュニケーション学科の学生5名が見事合格しました。内訳は以下の通りです。
| 高等学校 | 国語 | 1名合格 |
| 中学校 | 国語 | 1名合格 |
| 英語 | 4名合格 (追加合格含む 2025年11月26日変更) |
今年度も多くの先生方 (外部講師も含む) にご協力いただき、現場の声を踏まえた面接練習を行うことができました。また、休み時間に学生が各自で集まり繰り返し面接対策に熱心に取り組む様子も見られました。
来年度以降も大学として教員採用試験対策に関して十分なサポートを続け、多くの学生が教員採用試験に合格することを目指していきます。
そして、長崎純心大学卒の教員と学生との交流を一層強化できればと思います。
学生からのコメント
高等学校国語合格 (Yさん)
教員採用試験の勉強にどう取り組んだか
2次試験に向けては、純心大学の先生方や外部の先生方、教員を共に目指す仲間と共に面接対策を重ねました。面接対策ノートを作成し、常時手元に持ち歩きメモや確認をいつでもできるようにしていました。高等学校の面接には模擬授業があるため、本番と同様の時間配分で過去問を全て行いました。同期や先生方に可能な限り多くの模擬授業を見てもらい、改善点や良かった点などのアドバイスをいただきました。本番はもちろん緊張しましたが、積み重ねてきた面接対策を信じ自信をもって挑むことができました。徹底的に対策が行えていたことで、予想外の問題や質問が飛んできたときにも自身の考えや思いを焦らず十分に言葉にして伝えることができたと感じています。
純心大学は試験に対して、先生方のサポートが手厚く、仲間と共に思う存分に努力ができる環境が整っていると感じました。試験に向けて不安に押しつぶされそうな時、しんどさを感じる時も多々ありましたが仲間と互いに励まし合い、先生方の優しい声掛けによって踏ん張ることができたと思います。応援してくださった人々全員に感謝しています。
どういう教員になりたいか
教科の専門性を高められるように努力を重ね、「国語ってこんなに面白かったんだ」と興味を持ってもらえるような授業展開ができるような教員になりたいです。
また、生徒一人ひとりとのコミュニケーションを大切にし、生徒の学びや心理面を支えられるような教員になりたいです。1日でも早く、生徒や教員の先生方に慕ってもらえるように精進していきたいと思います。
中学校国語合格 (Tさん)
教員採用試験の勉強にどう取り組んだか
大学推薦をいただけたため1次試験は受けていませんが、推薦をいただけるまでは東京アカデミーさんが出版しているセサミノートと問題集を活用し、平日の日中はひたすら暗記、夜(帰宅してから)は問題集を解いていました。土日には過去問を解き、覚えていなかった・知らなかった単語や、間違えた問題にはセサミノートに印を付け、セサミノートの方に解説などを詳しく書き込み、セサミノートを自分だけの参考書になるようにしました。過去問は遡れるだけ遡り、推薦が決まってからは解かなくなりましたが、7年分は遡りました。
2次試験については、外部の先生や大学の先生に何度もご指導をいただき、言葉選びや回答のしかたなどを相談しながらブラッシュアップしていきました。また、面接練習を行っている様子を動画に撮ってもらったり、録音したりして、何を言ったのか、どのような答え方(姿勢、目線、イントネーションなど)をしたのかを後から確認できるようにしました。
課題面接についても、できるだけ過去問を遡り、10分で考えて2分で回答する練習を1人、または友人や先生に見てもらいながら行いました。
その後、改めて指導要領などを見ながら回答を考え直し、考え直した回答をまた2分で話す、という繰り返しを行いました。そうすることで、似た問題が出た際に、「ここは指導要領のここが使える」などの発想がすぐに出てくるようになりました。
最後に、過去問は遡れるだけ遡ることは大切だと思います。そうすることで、傾向を掴むことができるうえに、どのような問題がきてもある程度対応できるようになるためです。また、面接については、大学の先生や友人を頼り、何度も練習することが大切です。
どういう教員になりたいか
私は、中学生の時に自己肯定感が低くなってしまった経験があるため、今の中学生には私と同じ思いをさせないよう、生徒一人ひとりを認め、どんなことがあっても決めつけたりせず向き合い続ける教員でありたいです。学校にいる生徒全員と向き合うことはどうしても難しい場面があると思います。しかし、自分が受け持っているクラス、部活の生徒などの関わりがある生徒とは確実に向き合い、どんな時も味方でいられるようにしたいです。また、直接の関わりがない生徒であっても、毎日の休み時間や掃除の時間などスキマ時間の様子を使いしっかりと観察し、変わったところがないか、落ち込んでいないかなどを見守ったり声をかけたりしていきたいです。
授業においても、一方的に話すだけの授業ではなく、「楽しく理解できる」をコンセプトに、全員が楽しくしっかりと理解できる授業を行っていきたいです。
中学校英語合格 (Aさん)
教員採用試験の勉強にどう取り組んだか
一次試験の勉強は、まず参考書やノートを用いて基本的な知識を取り入れ、それから過去問を解いて傾向をつかみ、間違えた問題には印をつけて正解できるまで何度も解いて反復するようにしていました。専門試験の英作文対策は、ゼミの先生に添削をお願いして自分が表現できる幅を広げられるよう努めました。
二次試験に向けては、自己分析を早い段階から始め、面接ノートを作りまとめるようにしていました。面接練習が本格的に始まってからは、様々な先生方に積極的に面接練習をお願いし、話がまとまらなかった部分などはもう一度自分の中で良く考え直し、復習する時間も大切にしていました。対策期間中は焦りや不安でいっぱいになることもありましたが、必ず夢を叶えるという強い気持ちと先生方からの多くの励ましの言葉で乗り越えることができました。
どういう教員になりたいか
4月から教壇に立つにあたって私が目標にしている教師像は2つあります。
1つ目は、生徒との信頼を築く教員です。今後教員として、指導をしていく場面が増えてくると思います。私は、寄り添う指導だけでなく厳しさを持った指導も含めて生徒が心から理解して納得できる指導を行うためには信頼が必要だと考えています。多様化が進む中で、生徒一人ひとりの特性をしっかりと把握し、生徒が自分のことを理解されているという安心感をもてるよう生徒と向き合っていきます。
2つ目は、プロを極める教員になることです。教員は生徒に教科の基本的な知識や技能をきちんと教えていく必要があります。できる限りどの生徒にも理解しやすく英語の楽しさが伝わる授業ができるよう、日々、反省と改善を繰り返しながら研究を重ねていきます。教員という職を選んだからには教育者としての指導力や授業力を極める覚悟を持って仕事をしていきたいです。
中学校英語合格 (Rさん)
教員採用試験の勉強にどう取り組んだか
1次試験の勉強は、東京アカデミーが出版しているセサミノートを活用しました。セサミノートに書いてあるものを何周もすることによって、徹底的に暗記することを心がけました。他にも、問題演習を重ねるなかで、自分の苦手を把握し克服することを心がけました。
2次試験では、面接が行われます。一般面接の練習では、友人とお互いに面接練習を行ない、自分自身でも様々な質問を考えて、それに応えられるように準備をしました。また、空きコマや、全休の日を利用して多くの先生に毎日面接の練習に付き合っていただきました。課題面接に関しても、毎日先生方に協力していただきました。「10分で考え、2分で説明する」というのを実践しながら、時間の感覚を掴むことを心がけました。一人で行う時はスマホで録音し、それを聞き直してきちんと伝えたいことが伝わっているかを確認しました。内容に関しては、今までの英語科教育法の授業で行ってきたことを踏まえ、文部科学省が出している授業動画を見て授業の流れを理解することを心がけました。
今回の試験を通して、教員採用試験の練習に貴重な時間を割いてくださった先生方、いつも励ましてくれた友人や家族に改めて支えられていると改めて感じました。本当にありがとうございました。
どういう教員になりたいか
私は、多様化してきている現代で、生徒一人ひとりの思いや個性を尊重し、何事にも前向きに挑戦できるように生徒を支える教員になりたいです。中学生という貴重な時期を任せてもらっているという自覚を持ち、学び続けていくことで生徒にとって、より良い教育の環境を提供していきたいと考えています。授業はもちろんのこと、授業以外の時間での生徒との関わりを通して、一人ひとりの生徒と真剣に向き合い、共に成長できる教員になりたいと思います。
中学校英語合格 (Kさん)
教員採用試験の勉強にどう取り組んだか
教員になるのは保育園の頃からの夢であり、教員採用試験に向けて、日々の学びを積み重ねることを大切にしました。特に意識したのは、「継続して学習に取り組むこと」と「仲間と支え合いながら挑戦すること」です。まず一次試験に向けて過去問を何度も解き、間違えた問題には印をつけ、何度も解き直しました。また、同じ教員を目指す純心大学の仲間と協力し、支え合うことで自信をもって一次試験に臨むことができました。
二次試験においては、外部から指導に来てくださった先生方をはじめ、多くの先生方に協力していただき、面接練習を重ねました。時には上手く答えられず、不安や焦りを感じることもありましたが、仲間とともに努力を重ね、先生方からの助言を素直に受け止めながら準備を続けたことで、本番では過度に緊張することなく、落ち着いて自分の思いを伝えることができました。
どういう教員になりたいか
将来は、生徒一人ひとりの個性を尊重し、安心して挑戦できる温かな学級を作りたいです。特に英語の授業では、生徒に「英語って楽しい」と感じてもらえるように授業を工夫し、自ら進んで学びたくなるような場をつくりたいです。そして、私自身も常に学び続け、生徒とともに成長していける教員でありたいと強く思っています。
(記:三野)