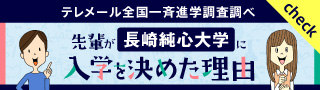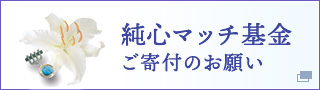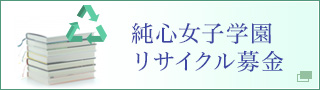ゼミ紹介
足立 耕平 ゼミ
3年前期では4名程度のグループとなり、研究テーマを決め、研究計画を立てて調査を行い、データを分析しレポートとしてまとめていきます。研究テーマは心理学に関連するものであればなんでも自由であり、これまでには記憶、音楽、人間関係、SNSなど様々なテーマで研究が行われてきています。また、研究成果は学内の合同ゼミ発表会で発表を行っています。
3年後期から4年にかけては各自が卒論完成に向けて取り組んでいきます。ゼミでの活動を通して、他者とコミュニケーションをとってプロジェクトを進めていく力や、様々なことに好奇心を持って取り組んでいく姿勢を養いたいと思っています。
井上 由起 ゼミ
ゼミではそれぞれが自分の関心のある研究テーマを設定し、ディスカッションをしながら学びを深めています。生活の中で感じた福祉に関する疑問、実習で感じた戸惑いやわからなかったこと、どうすればよかったのかと考えさせられたことなど、学生の皆さんの小さな気づきやつまずきを大事にしながら、お互いに高め合えるゼミを目指しています。
ゼミ生の声
井上ゼミは、今年から始まったゼミで、現在の3年生が一期生です。人数は少ないですが、その分一人一人の考えについて取れる時間が多かったり、すぐに仲良くなれたりするところも井上ゼミの強みです。井上先生も優しいのでとてもアットホームで過ごしやすいゼミです。講義では、それぞれ関心のあるテーマや先行研究について全員で意見を出し合って新たな気づきが出来たり、より関心のあるテーマを深堀りして明確にすることができたりします。
大杉 あゆみ ゼミ
私は高齢者に対する支援、特に認知症の人に対するケアに関心があります。誰でも認知症になる可能性があります。認知症になり生活の中で困ることが増え不安なときに、温かな言葉をかけそっと支えてくれる専門職がいてくれると、とても心強いと考えます。
高齢者介護だけでなく、社会には多くの福祉課題があります。ゼミでは、それぞれの学生が社会の中にある問題や関心事について、調べたり、対象者にインタビューしたりすることを通して、知りたかったことを明らかにしていきます。
卒業論文作成は大変なことですが、努力して取り組んだ先には大きな充実感があると思います。たくさん悩みながらも卒業論文や資格取得に向けた実習、就職活動と頑張る学生の姿から、私もたくさんのパワーをもらっています。
ゼミ生の声

私たち大杉ゼミでは、誰もが生活しやすい社会づくりを目的として研究しています。高齢者虐待や孤独死など、それぞれが関心のあるテーマについて調べ、発表し合います。そして、生きづらさを抱えている人々に着目しながら、どのような支援が必要なのかを話し合っています。
個性豊かなメンバーが集まり、アットホームな雰囲気の中、楽しく活動しています。
小川 さやか ゼミ
私の専門分野は心身医学、臨床心理学であり、人の心と体の関連について興味があります。現在は主に皮膚疾患とメンタルヘルスの関連について研究を行っています。また、大学生の学生生活への適応についても興味があり、質問紙法を用いて研究を行ってきました。 ゼミでは、3年前期は卒業論文作成の基礎を学ぶことを目的として、自分の興味・関心のある分野の学術論文を検索し、まとめる作業を行います。まとめたものをゼミ内で発表し、ゼミのメンバーと一緒に意見交換をしてもらいます。
3年後期からは各自が卒業研究に向けて、テーマ設定を行い、卒業論文の調査の準備を行います。ゼミのメンバーと話し合いながら、自分の興味・関心のあるテーマについて学び、設定したリサーチクエスチョンについてさまざまな視点から検討する力を養いたいと思います。
佐藤 ひとみ ゼミ
福祉実践の中で、支援の対象となる人や支援をする人それぞれが何を大切にしているのかを丁寧に見ていくための視点を身につけていくことを目指して、さまざまな文献を読んだり、ディスカッションを行います。
学生の間に他者のさまざまな意見を聴き、受けとめ受けとめられる貴重な経験を積んで、かかわる人々を大切にできる人材になっていってほしいと思っています。
卒業論文の執筆にあたり、ゼミ生相互で意見交換をし、内容を練っていく協働作業を大切にしています。
ゼミ生の声
4年生:アイスブレイクやレクリエーションを通してゼミ生の仲がとても良く研究もお互いに協力しながら進めています。 佐藤ゼミは学生主体、学生の意見を否定せず受け止めてくれるゼミなので、とても相談し やすく、自分の考えを広げることができるゼミです。 佐藤先生とゼミ生全員、一丸となり卒業に向けて頑張っています。 「卒論は個人戦ではない!団体戦!」
3年生:佐藤ゼミでは、三年前期はテキストクリーティークを活用し論文について理解することから始めました。自己理解を深めるためにも、個人ワークが多かったです。実際に四年生の論文の中間発表を聞き、より論文に対しての理解が深まりました。 佐藤先生は、文献検索の方法や論文作成について優しく丁寧に教えてくれます。また、論文のテーマに悩んでも一緒に考えてくれます。先生がのんびりしているのでゼミの雰囲気もとても落ち着く空間になっています!
澤 宣夫 ゼミ
私の担当する科目や専攻演習(ゼミ)では、福祉実践の基礎となる考え方や思想をともに考え、専門的な援助者となっていくための土台を作っていくことを目指しています。福祉の実践には、専門的知識や技術だけでなく、何を大切にしていくかという価値観が必要です。学生のうちに、そのことを考えて続けて、絶えず自分と向き合うことができるようになっておくことが、将来専門職として、誇りと自信を持って活躍していくことにつながると信じています。お互いに高め合いましょう。
白濱 あかね ゼミ
3年生前期には、他学生とディスカッションを行いながら、基本的な論文の読み方や書き方について学んでいきます。3年生後期には、それぞれ興味関心のある分野やテーマについての先行研究をレビューし、ゼミ内での発表を重ねるなかで、自分の卒業論文のテーマを模索してきます。4年生では自分の関心のあるテーマに沿って研究を進めていきます。
ゼミ活動を通して、自分の興味関心から具体的な問いを立てて検討していく力や、他者とコミュニケーションをとりながら自分の力で物事を進めていく力を身に着けていくことを目指しています。
田崎 みどり ゼミ
日常生活ではさまざまなことが起こります。いいことだけでなく、嫌なことも少なくありません。そんな時、自分を支えてくれるものの一つが自分の持っている興味や関心です。このゼミでは自分の興味・関心に改めて目を向け、じっくり卒論のテーマを絞り込んでいきます。
心理学ではどのように研究されているのか、いないのか。研究されていないとしたら、なぜなんだろう?そんな素朴な疑問を心理学的な視点から捉え直し、みんなでいっしょに考えていくことを目指しています。
ゼミ生の声

田崎ゼミは、それぞれが設定したテーマに沿って個人のペースで研究を進めています。3年生の段階で基本的な論文の書き方を学び、自分の研究に必要な文献を集めたり予備調査を行ったりと、卒論に向けた活動を開始することができました。 先生がゼミ生一人一人に合わせて指導、サポートをしてくれることに加え、ゼミ生同士でも協力し合う空気感が自然にできていると感じています。落ち着いた雰囲気の中、毎週楽しく過ごすことができるゼミです!
飛永 高秀 ゼミ
ゼミでは、事象としての社会福祉の実態をいかにして捉えて行くのかを制度・政策、援助実践・理論などの枠組・視点から検討しています。現場実践に偏ることなく、体系的にそして客観的に社会福祉を捉えることの重要性を考えて行きたいと思っています。
教員の関心は、社会福祉において「住む」ことが生活の中でどのように位置づき、意味づけされ、それが福祉実践にどのように生かせるのかなど、居住概念の検討、高齢者等の居住支援システムですが、ゼミでは各学生の興味関心に基づき卒論を指導しています。
また、ゼミの縦と横のつながりを重視し、年に1回ゼミのOBOG会(研究会)を開催しています。研究会では、ゼミ卒業生の各領域における現場実践報告を行い、現状の理解と課題解決に向けての取り組み等について参加者で共有し議論をしています。
これらの活動はゼミ卒業生の事例検討の機会、そして、在学生が卒業生の仕事や学生時代の勉強、実習、就職等について話を聞く機会ともなり、とても有意義な時間となっています。ゼミ卒業生の現場実践での成長と活躍が私に大きな力を与えてくれます。ゼミ卒業生の福祉実践を今いる在学生に伝え、繋げ、より質の高いソーシャルワーカーを育てていくことが私の使命ともなっています。
細野 康文 ゼミ
研究テーマについては、心理学や福祉学に関連するものであれば基本的に自由です。自分自身の関心をより深く探求する姿勢を大切にしています。
3年前期では、心理学の研究に必要なプロセスである、テーマの設定や、研究計画の立案、調査・分析、結果・考察などを、グループ研究を通して学びます。また、研究成果については、他のゼミとの合同発表会を行っています。
3年後期からは、個別に卒論研究計画を立案し、4年前期からは、調査や分析、卒業論文の執筆を行います。卒業論文の制作はそれぞれの進捗に合わせて指導を行いますし、最終的には自分で作成するものですが、ともに学ぶゼミ生同士でお互いに助け合い、積極的に意見交換を行うことを大切にしています。
また、個人的にゼミ内での積極的な交流を期待していますので、ゼミでの交流企画などはゼミ生からの要望があれば積極的にサポートします。
松永 大介 ゼミ
当ゼミでは、児童の権利擁護や児童虐待などの現代的課題について学習を行います。ゼミ生はそれぞれ興味のあるテーマを設定し、児童福祉に関する文献を渉猟したり、分析したりして研究を進めています。加えて、ゼミではディスカッションを通じて児童のニーズについて多角的に考え、児童が健やかに育成される社会の実現に向けて議論を深めています。
そして、ゼミ生の皆さんには、自分の目線でテーマ設定し、独自の視点から児童福祉の課題に切り込んでほしいと思っています。その過程で得られる学びは、将来、社会で活躍する際の貴重な力になると確信しています。ゼミ生の可能性を信じ、それぞれの成長を心より楽しみにしています。
丸山 仁美 ゼミ
なぜ私は人の目が気になるのか、なぜ私は傷つくことが怖いのか、なぜ私は生きることにむなしさを感じるのか…。臨床心理学を学ぶことは、そんな「なぜ私は…?」という疑問に自分なりの答えを見つけ出すことだと私は思います。このゼミでみなさんが自分自身に対する何かの答えを見つけられたらよいなと思っています。
心理学ではどのように研究されているのか、いないのか。研究されていないとしたら、なぜなんだろう?そんな素朴な疑問を心理学的な視点から捉え直し、みんなでいっしょに考えていくことを目指しています。
ゼミ生の声

丸山ゼミでは、3年の前期という早い時点からゼミ生一人一人が自分の興味関心のあるテーマを設定し、それについての研究をしています。ゼミ生の研究テーマは「同居と一人暮らしでは親子関係がどのよう違うか」や「服装の色が印象をどのように左右するか」や「失恋から立ち直るために何が重要か」など本当に様々です。先生が指導してくれるだけでなく、他のゼミ生から意見をもらうことでお互いを刺激し合いながら自らの研究を深めています。
三浦 佳代子 ゼミ
三浦ゼミでは3年次前期から後期の前半にかけて、卒業研究を進める上で必要なスキルを身につけるため、実際の研究のプロセスを全体的に体験し、研究の型を学びます。個人研究が基本ですが、「アイデアの絞り込み」「リサーチクエスチョンの検討」「研究方法の選択と仮説の立案」「結果の整理」などのステップを全員が同じペースで進め、ゼミ生同士でアイデアの共有や意見交換を行います。他者のテーマにも興味関心をもち、他者を尊重し、「持ちつ持たれつ」の関係を築いてほしいと思っています。
また、前期は毎回アイスブレイク係を決め、みんなで交流する機会を設けています。「まとまる時はまとまる」ことを大事にしている点もこのゼミの特徴です。
3年次後期では、興味のある分野の論文を読み、要約し、発表する練習を繰り返し、卒業研究のテーマを絞るための準備を進めます。
4年生は各自のテーマや目標に基づいて自分のペースで卒業研究に取り組みます。スライドの作り方、プレゼンの練習も積極的に行なっています。
吉本 知江子 ゼミ

3年次前期には、障がいを持つ方々の生活のしづらさや、障がいを持つ方の環境に焦点を当て、どのような条件が整えば、障がいのある人もない人も共に生きることができる共生社会が実現できるのか、ブレーンストーミングの手法を用いて、ディスカッションを行い、これらの結果を報告としてまとめるなどの学習を行っています。
3年次後期には、それぞれ関心のある分野の先行研究をレビューし、レポートに纏め報告を行っています。
4年次は専攻研究のレビューを基に、明らかにしたいテーマを定め、卒業論文の指導を行っています。
卒業論文の作成を通して、障がいについて様々な視点から理解するとともに、自分自身で問を立て、これらの問いを実証的に明らかにする力を身につけていただきたいと考えています。
ゼミ生の声
吉本ゼミは、障がいのみでなく、貧困や社会的排除など、様々な事例をもとに皆でディスカッションを行ないながら理解を深めていっています。
ゼミ単位でサポーターとして参加している純心カレッジ三ツ山塾では、障がい者の方と一緒にダンスをしたり、クッキーを作ったり、長崎さんぽに参加したりと、様々な活動を行ないながら障がいについての理解を深めていっています。
また、ゼミ以外でも、学生同士で定期的に集まり親睦を深めています。4年次には、それぞれのテーマをもと皆で協力し合いながら卒論を進めつつ、国家試験も全員合格を目標に日々精進しています。
卒業論文
本学では、3年次から専攻演習(ゼミ)を選択し、そのなかで卒業論文を作成することになっています。
卒業研究では、ゼミの担当教員の指導を受けながら、学生自身で設定したテーマについて文献研究や調査・実験などを行い、論文としてまとめていきます。卒業論文のテーマとしては以下に示すように福祉や心理に関する様々な内容が扱われています。
卒業研究テーマ一覧
- 子ども食堂に関する一研究
- 発達障害児の保護者支援に関する一研究
- 高齢者施設に勤務する介護職員のやりがいについての一研究~介護福祉士へのインタビュー調査を通して~
- 医療ソーシャルワーカーの地域におけるネットワークづくりの課題に関する一考察~医療ソーシャルワーカーへの聞き取り調査を踏まえて~
- がん患者の在宅医療を視野に入れた医療ソーシャルワーカーの支援に関する研究
- 里親制度推進のための自治体の取り組みに関する研究
- 地域包括ケアシステムにおける社会福祉士の役割に関する一研究
- 劣等コンプレックスと自意識の関連についての研究
- スチューデントアパシー傾向に関連する要因についての研究
- ネガティブな経験が人格発達に及ぼす影響についての研究
- 大学生のネガティブな事象に対する思考と注意のプロセスの検討-スクラッチアートを用いたマインドフルネス作業と注意分割気晴らしの比較を通して-
- 浮気や不倫に関する情報への接触が若者の結婚観に与える影響について
- 赤ちゃん動画の視聴が及ぼす人々への癒し効果についての検討-「動物」と「ヒト」それぞれの赤ちゃん動画を用いて-
- SNSにおける商品口コミの評価の程度や売り込み意図の有無が商品評価に及ぼす影響
- VRゲームにおけるフロー体験および身体的所有感の特徴について
- パーキンソン病における展望記憶障害についての検討