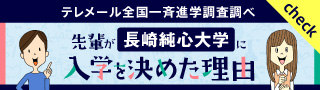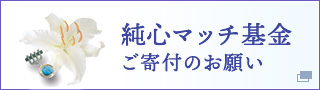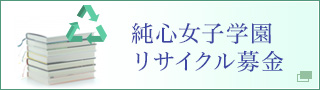2025年5月14日(水)、福祉・心理学科の科目「ソーシャルワーク演習Ⅳ」にて、長崎市地域コミュニティ推進室の皆様を講師としてお招きし、「長崎市における地域コミュニティをささえるしくみ」についての講義が行われました。

講義では、長崎市が直面している人口減少や少子高齢化により、地域のつながりが低下し、さまざまな地域課題が浮き彫りになっている現状について学びました。そこで、地域のつながりを支えるためのしくみとして、地域の団体同士の連携を強化する「地域コミュニティ連絡協議会」が設立され、地域住民がどのように地域課題に取り組んでいるかを学ぶことができました。
実際に取り組まれている地域活動を動画でお示しいただき、学生同士でのディスカッションの時間を通して学生の意見を共有できたことで、学生も非常に良い学びの機会となりました。
学生の声
- 長崎市は高齢者の人口が増加している反面、人口や若者の数、自治会の加入率は年々減少しており、今後も同様に変化していくことが予想されている。加えて、核家族化や価値観の多様化等、地域を取り巻く状況が同時進行で変化している。これにより、自助・互助・共助・公助の力の低下、コミュニティ力の低下が起こり、様々な地域課題が表面化しているという危機的状況にある。このことから、誰もが暮らしやすいまちであり続けるには、地域の現状と今後予想される傾向をもとに、地域の力を活用し、住民同士のつながりや時代の変化に応じた助け合いのしくみをつくることが必要だと理解した。そして、これらの現状や課題に対し、長崎市では地域コミュニティ連絡協議会(地コミ)の設立が進められていると学んだ。地コミによって行われている地域活動には、地区ごとに特色があった。同じ長崎市内であっても地区によって特徴や強み、あるいは取り組むべき課題が異なっており、そこにはその土地の生活者だからこそ気づけるものもある。そのため、地域の力を活かした地域づくりには、地域住民とのディスカッションや活動を通して生活者の意見を取り入れ、住民とともに様々な社会資源を発見・活用することが大切だと感じた。
- 今回の地域コミュニティ活動の講話を聞き、長崎の現状と地域コミュニティが必要な理由について理解することができた。加えて、長崎で実行しているコミュニティ活動がどのようなものがあるかや、どのように実行に移しているかについて知ることができたと感じている。具体的に2つ考えたことがある。1つ目は長崎の人口の流出に伴って地域コミュニティが必要になってきていることである。長崎の人口流出は全国的にみても多いため、地域住民が減少している。加えて、核家族化により家族で助け合うことが難しいことや地域とのつながりがないことが現状である。これらから、地域で助け合う環境整備を行っていき、地域コミュニティの形成、活動を行っていくことが必要であることを理解し、考えることができた。2つ目は自分が住んでいる地域に地域コミュニティはあるかについてである。自分の理想の地域形成についてのワークを行った際に自分の地域について考えた。自分の地域では高齢化が進み、地域で助け合うことが必要であると考えている。そのため、地域で交流がより生まれる活動や災害時に助け合うために一人暮らしをしている高齢者がどのくらいいるかについて把握していくことも大切であると考えた。また、自分が所属している小学校の校区は広いため、小学校の校区での地域コミュニティの形成では、十分な体制を作れているか考え、もう少し狭い範囲で作るべきところや自治会での活動を積極的に行うことのできる環境や人員について考えて行くことも必要であると考えた。
- 今回は、地域コミュニティ活動について学ぶことができた。地域コミュニティ活動とはその名の通り地域コミュニティの場を作る活動を行うことであり、長崎をよりよくするために様々な活動が多くの団体を通してつながり合いながら行われているのだなと思った。私自身、長崎市の消防団に所属しているが、消防団も地域のイベントがあると要請が入り、子どもたちから高齢者にかけて幅広い年代を対象に防災導等を行っている。こうした活動も地域コミュニティ活動の一つなのだなと思った。他にも自分たちの自治会ではクリスマス会や餅つき大会、胸骨圧迫指導、清掃活動などの活動を行っており何度か参加したことがある。しかしS小学校地区のみらい会議のような意見交換会などは自分たちの地域で行っているのか耳にしたことはない。そのため、いつどこにそのような活動が行われていることを知らせているのか掲示板などを確認していこうと思う。
担当教員:大杉・飛永・松永・福田・鹿山