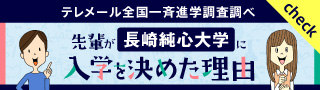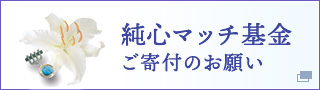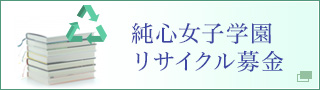7月7日(月)の「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」にて、本学の卒業生で「多機能型事業所たちばな」児童発達支援管理責任者の松永奈菜先生に講師としてお越しいただき、夏季休暇中に実習(ソーシャルワーク実習Ⅰ)を予定している実習生に向けて、実習の心得や実習生としてのマナーに関してお話をしていただきました。

受講した学生たちは実習に臨むにあたり、実習での笑顔の大切さや利用者との関わりが自分を見つめ直す機会となることを学ぶことができました。
松永先生が真摯に利用者の方と向き合う実践を目の当たりにし、学生たちにとってとても有意義な時間となりました。
学生の感想
- 松永先生の講話を聞いて、自分がした質問(今までの学生の記憶に残る行動や好印象だった学生の行動は)に対して、質問をするや、挨拶をするなどの基本的な事はもちろんだが「主役は利用者であると言うことを忘れない」という回答があったことがとても記憶に残っている。自分は講話を聞くまで、ソーシャルワーク実習に対してものすごいプレッシャーを感じており、不安感が拭えなかった。自分のする行動に責任が伴うため、絶対に失敗してはならないと言う考えが私の中にあったからだと思う。しかし、「主役は利用者である。」という言葉を聞いたときに、はっとした。自分は実習にいかせてもらう立場で本来は、実習指導者たちが利用者さんのために働いている場であり、そこに後から行く私は、学生だからと変に緊張していた。クライエントの意思あってのソーシャルワークだと言う事は、知識としてはわかっていたが、自分の頭から抜けていたことを自覚した。これが自己覚知なのかと感じた。考えていることが「利用者」なのか「自分」なのか履き違えないように徹底しようと思う。
- 実習指導者の講話を通じて、ソーシャルワーカーとしての専門性や倫理観の大切さを改めて実感しました。特に印象に残ったのは、笑顔で明るく話しかけることが大切、楽しむことが大切という言葉です。実習と聞くと精神的にも体力的にもきついというイメージが強かったけどこの言葉を聞いて学べることを楽しみながら笑顔で実習を行いたいと感じました。また、実習だからこそ学べる利用者さんや職員さんとのコミュニケーションの仕方、距離のとり方などを職員さんの真似しながら自分のスキルにしていきたいと思いました。わからないことがあってもわからないままにせず、質問をして知識を増やしていきたいと思いました。実習日誌では、自分中心に書くのではなく、利用者さんを中心に書くことが大切だと学びました。これからの実習では、利用者さんの声をよく聴き、その思いを尊重した支援を心がけるとともに、松永さんの言葉を行動に反映させていきたいです。講話で得た気づきを、今後の学びと実践にいかしていきたいと強く感じました。
- 今回の講義を受けて、実習に向けてどんな準備や心構えが大切なのかを知ることができました。特に、「実習は自己覚知の種」という言葉が印象に残りました。実習を通して自分がどんなことに腹を立てるのか、嫌な事をされた時にどのような感情になるのか理解し、自身の感情・行動を客観視して感情をコントロールすることができるように実習を通して学びたいと感じました。また、実習先では挨拶や笑顔を忘れないこと、わからないことは質問をするなどを大切にすることを改めて認識しました。特に「笑顔」は、自分では笑顔でいるつもりでも緊張していると顔がこわばってしまうので、自分の表情には常に気をつけたいと思いました。実際に利用者の方と関わることで学べることがたくさんあると思うので、積極的にコミュニケーションを図り、利用者の方だけでなく職員の方ともコミュニケーションを図り、信頼関係を築いていきたいです。実習で利用者の方と関わる中で、自分にできることを1つずつ見つけて、前向きに楽しく取り組んでいけたらいいなと感じました。
担当教員:大杉、飛永、松永、福田、鹿山