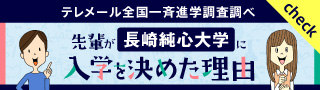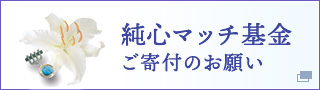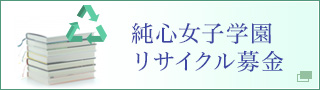長崎県の福祉保健課地域福祉班から「民生委員・児童委員の認知度向上の取組」への協力依頼により、ソーシャルワーク演習Ⅱの授業の中で「民生委員・児童委員の方と学生の座談会」が開催されました。6/26に行われた「民生委員・児童委員の役割と活動内容について」の講義に続く、第二弾の取り組みです。
座談会
座談会では、14名の民生委員・児童委員に参加していただき、取り組まれている活動内容や実際に感じられている民生委員・児童委員の課題について学生と共有することができました。また、学生からも多くの質問を行うことができ、民生委員・児童委員の知識を高めることに繋がりました。
グループ発表
座談会後は、各グループからの発表を行い、座談会を通して学ぶことができたことを発表し、民生委員・児童委員の未来に向けた前向きな意見を聞くことができました。
学生の感想
学生の学びについて、下記に学生の感想を紹介します。
- 今回初めて直接民生委員の方のお話を聞く機会があり、普段なかなかこのような機会がなかったのでとても貴重な時間となりました。民生委員の方のお話で地域との繋がりのためには、1番はコミュニケーションによって信頼関係を築くことが大切だということがわかりました。コミュニケーションは、直接顔を合わせて話すのでお互いの表情が分かりながら話すことができ、相手の言葉以外の態度なども把握することでより深く理解でき、これからの信頼関係構築にも繋がるということが理解できました。また、若い世代はなかなかこのような活動を知る機会がないと思うので、私たちが身近な人達に広めていくことも重要なのかなと思いました。
- 今回、民生委員の方から、民生委員は、地域の人の相談を「解決する」のではなく、「専門職につなぐ」という橋渡しの役割を担っているというお話を聞き、それがとても印象に残りました。また、相手の話に耳を傾け、まずは受け止めるということが大切だというお話は、私にとって大切な学びとなりました。これは民生委員だけでなく、福祉のさまざまな活動に共通して求められる姿勢だと感じました。誰かを支えるには、まずその人の思いや状況を否定せずに受け入れることが出発点であり、その土台があるからこそ、次の支援やつながりに進めるのだと学びました。さらに、民生委員の活動には、人手が足りず、活動が十分に理解されていない現状があるという課題があることも知ることができました。そして、町内会の中には、民生委員の仕事を「簡単なこと」と捉えてしまう人もいるという話には、地道な活動がどれだけ見えにくいものなのかという現実を感じました。そのため、これから自分が地域に関わる立場になったとき、ただ支援される側ではなく、支える側の視点も持てるように意識していきたいと思います。
- 民生委員の皆様は非常に多忙な職務を抱えていらっしゃるにもかかわらず、終始明るく笑顔を絶やさずに活動内容について丁寧にお話ししてくださいました。その姿からは、単に「大変そう」という印象や「なりたくない」といったネガティブな感情は一切感じられず、むしろ地域のために尽力することへの誇りややりがいが伝わってきました。実際の活動の具体例や、住民一人ひとりに寄り添う姿勢を伺うことで、民生委員の仕事の意義や重要性を改めて実感するとともに、これまで抱いていた民生委員の仕事に対する不安や抵抗感が払拭されました。今回の座談会を通じて、民生委員の皆様の温かさや献身的な姿勢に触れ、地域福祉の現場で果たしている役割の大きさを深く理解することができ、大変有意義な時間となりました。
なお、当日は長崎国際テレビの取材も入り、座談会の様子はテレビで放映されました。
https://news.ntv.co.jp/n/nib/category/society/niced75a7a744f4a638fb757c1a99539d7(外部サイト)
担当教員:飛永、大杉、佐藤、鹿山