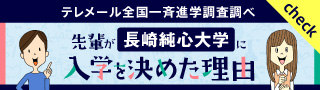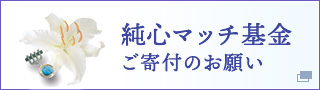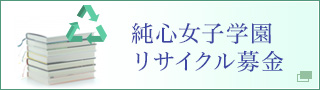福祉・心理学科では1年生の「ソーシャルワーク演習Ⅰ」の授業の一環で11月1日(土) 11時から14時まで、長崎県こども家庭課主催の「児童虐待防止推進街頭キャンペーン」(みらい長崎ココウォーク3階ココスクエア)に協力し、啓発活動を行いました。
学生たちは、「児童虐待防止にご協力をお願いします」と声をかけながら、自分たちが手作りしたオレンジリボン(作成の様子はこちらの記事で)やリーフレット、ポケットティッシュを配布しました。最初は緊張した様子も見られましたが、次第に積極的に声をかけることができ、児童虐待防止の大切さを伝えていました。受け取ってくださった方々の中には、学生たちに「頑張ってね」と励ましの言葉をかけてくださる方や、リーフレットをじっくり読みながら関心を示してくださる方も多く見られました。
今回の活動を通して、学生たちは児童虐待防止の重要性を実感し、福祉専門職を目指す者としての自覚を深めることができました。また、事前学習から街頭キャンペーンまでの一連の取り組みの中で、地域社会における支援のあり方や、一人ひとりにできることについて深く考える貴重な機会となりました。
ご協力いただきました長崎県こども家庭課の皆さま、会場をご提供いただきましたみらい長崎ココウォークの皆さま、温かく見守り励ましてくださった市民の皆さまに心より感謝申し上げます。
学生の感想
- オレンジリボン運動を通して市民の方々に子どもの虐待防止について考えるきっかけを提供できたことには大きな意味があったと思う。また、啓発活動を行う中で「どのように伝えるか」を自分なりに考え直すことができたことも貴重な経験だった。授業で学んだ知識を教室内にとどめるのではなく、実際に地域の方と関わりながら考えたことで、自分の理解もより深まったと感じている。
- 一人でも多くの人に知ってもらえばいいなと思いながら最後までできました。活動を通して、児童虐待は身近な問題であり、一人ひとりの意識や行動が子どもたちを守る力になると感じました。これからも今回の活動や知識を生かしてボランティアに参加したりして、子どもが安心して暮らせる社会づくりに少しでも貢献していきたいです。
- 子どもを守るためには、行政や専門機関だけでなく、地域や一人ひとりの関心が欠かせないことに改めて気づきました。私自身、大きな力にはなれずとも、困っている子どもや保護者の方を見かけた際には、相談窓口の存在やその有効性を伝えたりするなど、小さな行動からでも支援につなげたいと思いました。オレンジリボン運動を通して、自分にもできることがあり、それを学習して成長していきたいという意識が芽生えたことが、今回の最も大きな学びでした。
- オレンジリボン運動を行って、人々に児童虐待防止のことを知ってもらうだけでなく私自身も児童虐待防止についての意識が高まりました。それと同時に、もっと多くの人に11月は児童虐待防止推進月間ということを知ってほしいと思いました。多くの方が児童虐待の現状を知ることによって、早期発見が増え児童虐待が減り、いずれはなくなる未来がくると私は信じています。オレンジリボン運動が私にとってその未来に近づくための第一歩になりました。今後も児童虐待を防止するために私たちが出来ることは何なのか考えていこうと思います。
- 社会福祉士を目指す立場として、実際に地域の人々と啓発を行うことの大切さを強く感じました。ティッシュやチラシを配る中で、ただ配布するだけでは関心を持って もらえず、笑顔で声をかけることや目的を簡潔に伝えることが大事だと学びました。特に 子どもたちはがんばくんやらんばちゃんに興味を示し、一緒に写真を撮影する姿が微笑ま しく、「子どもを守る社会」を目指す活動の意義を実感しました。
- この体験を通して「オレンジリボン運動」や「189」の存在を知らない人は多いということに気づくことができました。児童虐待防止のためにはこのような活動を増やして継続していくこと、私たちのような福祉に関わる学生が中心となって児童虐待に対する関心や知識をもっと深めていくことが求められるのではないかと考えました。
- オレンジリボン活動を知らない人も多くいたのでそこで自分の言葉で話すことでこの活動で学んだ知識や考えをより深めることができたと思います。しかし聞かれたことに対してわからないことや答えられない場面もあったのでそこはしっかり勉強して自分の知識として蓄えるようにしたいと思います。
- 児童虐待防止のための活動は、ただ言葉で伝えるだけではなく、こうして人と直接関わることでより多くの人に思いが届くのだと思いました。オレンジリボンに込められた「子どもたちの未来を守る」という願いを理解したうえで配ることで、自分の行動にも責任と想いを持てたと思います。
- 活動を通して、社会からの関心を得てもらうためには、まず福祉について学び、関わりを持っている私たちが関心を持ち、正しい知識を得て、今回の活動のように声をあげて発信していくことが大切だと思った。また、このようなリボンを配るという小さな行為でも、声を掛け、説明し、問題に気付いてもらうことで、誰かの児童虐待への意識を変えるきっかけになる可能性を感じた。
- 子供たちが安心して生活できるよう社会を作るためには、周りの大人の意識を変えていくことが必要だと感じました。この経験を通して、自分の行動が小さくても、誰かを守るきっかけになるかもしれないと思いました。これからも、社会の課題に目を向け自分にできることはないか考え、行動していきたいです。
- 児童虐待は家庭だけでなく地域や社会で考えるべきであると思います。虐待に気づいた人には速やかに通告する義務があることから、自分にできることは小さいけれど、虐待かもと思ったら周りの大人に相談してみたり、189に電話を繋げるような意識を持とうと思いました。
担当:大杉、飛永、松永、鹿山