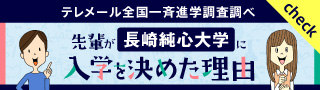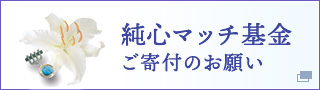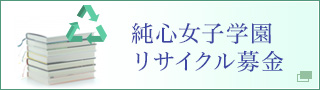カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
人文学部
【教育課程の編成】
人文学部では、卒業認定・学位授与方針(デイプロマ・ポリシー)を達成するために4年間のカリキュラムを「基礎科目」、「基幹科目」、「応用科目」の3つの科目群によって編成する。
【教育内容・方法等】
「基礎科目」は、人文学部の全学生に共通の科目群であり、思考力、判断力、表現力の基盤となる教養、外国語の運用力、情報処理能力並びに健康の基礎を身につけるとともに、地域社会の具体的な課題把握と解決のために主体的に学ぶ力を習得する。授業は、講義または演習形式で行う。
「基幹科目」は、各学科が目指す人材養成の目的を達成するために設けられた専門の科目群で、社会における自立のために必要な力を習得する。授業は、講義または演習形式で行う。
「応用科目」は、広く社会に貢献するために必要となる専門の学芸を知的かつ道徳的に理解し、応用する能力を習得する。授業は、人文学部の全学生が執筆する「卒業論文」につながる少人数のゼミナールである「専攻演習Ⅰa」「専攻演習Ⅰb」「専攻演習Ⅱa」「専攻演習Ⅱb」で行う。
言語文化情報学科
【教育課程の編成】
本学科は、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を達成するために「英語コミュニケーション専攻」「日本文化専攻」「世界の文化と長崎学専攻」「情報専攻」を設け、4年間のカリキュラムを「基礎科目」「基幹科目」「応用科目」の3つの科目群によって構成する。
【教育内容・方法等】
「基幹科目」は、学科共通科目と4つの学科専攻科目で構成し、言語・文化・情報の専門的知識と技能を高めながら、3年次から始まる卒業研究・卒業論文に取り組むための基盤をつくる。
- 学科共通科目は、「教養」「文献講読」「学術研究」の3つの分野で構成する。「教養」の分野では、地元である「長崎を知る」ための科目と世の中の時事を知るための科目を配置する。「文献講読」の分野では、文献を読み・まとめる・発表する・議論する能力を向上させるための科目を配置する。
「学術研究」の分野では、1年次に学科の各教員が専門とする様々な研究分野のことを知ることができる科目を配置する。 - 「英語コミュニケーション専攻」の科目は、「総合英語」「特定の目的のための英語」「アカデミック英語」「異文化理解・英語学・英文学」の4つの分野で構成する。「総合英語」の分野では、英語の4技能を統合し、CEFR B1レベル相当以上の英語力を習得するための科目を配置する。「特定の目的のための英語」の分野では、旅行、ビジネス、通訳、検定試験など、それぞれの目的に応じた英語力のスキルアップを図るための科目を配置する。「アカデミック英語」の分野では、さまざまなトピックについて情報を適切に取捨選択し、論理的な英語の文章を読み書きする能力を養うための科目を配置する。「異文化理解・英語学・英文学」の分野では、英語圏の文化や思想、文学を通して、英語という言語を多面的に理解する能力を高めるための科目を配置する。
- 「日本文化専攻」の科目は、「日本古典文学」「日本近現代文学」「日本の言語・文化」の3つの分野で構成する。「日本古典文学」の分野では、上代から江戸期までの原典資料を読解し、それぞれの時代の言語表現について実証的に学ぶための科目を配置する。「日本近現代文学」の分野では、近代・現代の文学作品を読解し、その理論や文学史を学ぶための科目を配置する。「日本の言語・文化」の分野では、日本語の様相を把握し、多様な文化の中で他者と対話する力を伸ばすための科目を配置する。
- 「世界の文化と長崎学専攻」の科目は、「世界の言語」「世界の文化」「長崎学」の3つの分野で構成する。「世界の言語」の分野では、中国語・韓国語・スペイン語の語学とその文化を学ぶための科目を配置する。「世界の文化」の分野では、日本、アジア、ヨーロッパを中心に世界の文化の多様性や豊かさ、思想、芸術、社会を学ぶための科目を配置する。「長崎学」の分野では、長崎の文化の特質を知り、地域的・歴史的比較の中で「長崎から世界を見る」、「世界から長崎を見る」ことでグローバルな見識を身につけるための科目を配置する。
- 「情報専攻」の科目には、「情報処理理論」「ビジネス実務」「マルチメディア演習」「Webデザイン・プログラミング」「AI・データサイエンス」の5つの分野で構成する。「情報処理理論」の分野では、コンピューターのハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、情報サービスの活用や情報セキュリティなどの知識を学ぶための科目を配置する。「ビジネス実務」の分野では、文書作成、表計算、プレゼンテーション、データベース等のオフィスソフトについて実務的レベルのスキルを習得するための科目を配置する。「マルチメディア演習」の分野では、画像処理の知識を学び、それらを活用して雑誌やポスター、動画等の制作ができるようになるための科目を配置する。「Webデザイン・プログラミング」の分野では、Webページ制作とプログラミングの基本を学び、Webサイト構築、実務処理の自動化、携帯端末用のアプリの開発等を学ぶための科目を配置する。「AI・データサイエンス」の分野では、AIの知識と活用方法を学ぶための科目と、データ分析に関する科目を配置する。
「応用科目」は、「専攻演習Ⅰa」「専攻演習Ⅰb」「専攻演習Ⅱa」「専攻演習Ⅱb」と「卒業論文」で構成する。なお、卒業論文の執筆は全員に課せられるが、詳細は専攻ごとに決定される。
文化コミュニケーション学科
【教育課程の編成】
文化コミュニケーション学科は、学位授与方針(デイプロマポリシー)を達成するために「日本文化専攻」「アジア文化専攻」「ヨーロッパ文化専攻」「長崎学専攻」「英語コミュニケーション専攻」「情報コミュニケーション専攻」を設け、4年間のカリキュラムを「基礎科目」、「基幹科目」、「応用科目」の3つの科目群によって構成します。
【教育内容・方法等】
「基礎科目」は、人間の人格性を基盤とする学部共通の教養教育として、幅広い視野と豊かな人間性を培うため、基礎科目として開設された一連の科目群(「導入・開発」「基礎教養」「言語文化・コミュニケーション」「情報・文献」「スポーツ・保健」「現代教養」)より修得すべき単位を定め、主体的に学ぶ力を修得します。授業は、講義または演習形式で行います。
「基幹科目」は、学科共通科目及び6つの学科専攻科目で構成され、内容及び方法において連携を深め、学習効果を高めるカリキュラムとなっています。
- 学科共通科目には、国内外のグローバル化社会の現状と歴史的背景やコミュニケ―ションのあり方等について幅広い教養が修得できる科目を配置します。
- 「日本文化専攻」には、日本文化について多方面から学修し、専門的な知識を修得できるように、歴史・語学・文学などの科目を系統的に配置します。
- 「アジア文化専攻」には、アジア文化の多様性と豊かさに着目し、その特質を修得するために地域についての多くの科目を配置するとともに、対象地域に様々な方法でアプローチするための科目を配置します。
- 「ヨーロッパ文化専攻」には、豊かな歴史と思想、芸術、社会を学ぶための科目を体系的に配置するとともに、現地での学習にもつながるように語学科目を充実させ、その文化的特質を体験できる科目を配置します。
- 「長崎学専攻」には、長崎の文化の特質を日本や世界との地域的・歴史的比較の中から学べるよう、広く歴史や文化に係わる科目を配置し、広い視野の中で長崎について学べる科目を配置します。
- 「英語コミュニケーション専攻」には、高度な英語コミュニケーション能力を養成するために英語の「読む」「書く」「話す」「聞く」の4技能を統合した少人数制科目を配置します。さらに英語コミュニケーションと情報コミュニケーションにおける統合的スキルの修得のための科目や、情報ソフトを利用し英語コミュニケーション能力を向上するための科目を配置します。
- 「情報コミュニケーション専攻」には、情報処理の基礎技能を全学生が習得できる科目や、オフィスソフトやマルティメディアソフトの高度なスキルを習得できる科目を配置します。
- 応用科目は「専攻演習Ⅰa」「専攻演習Ⅰb」「専攻演習Ⅱa」「専攻演習Ⅱb」と「卒業論文」で構成されます。なお、卒業論文の執筆は全員に課せられますが、詳細は専攻ごとに決定されます。
福祉・心理学科
【教育課程の編成】
本学科は、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を達成するために、「ソーシャルワークコース」「心理学・カウンセリングコース」「ケアワークコース」を設け、4年間のカリキュラムを「基礎科目」「基幹科目」「応用科目」の3つの科目群によって構成する。
【教育内容・方法等】
「基幹科目」は以下の4つの方針をもとに編成・実施をする。授業は講義、演習、実習形式で行う。
- 学科の全学生を対象として、自他の健康と幸福に貢献する力の基礎となる、地域社会や人々の多様性と共通性を理解する科目、人間の尊厳と人権を重んじる倫理観を育む科目を配置する。
また、生物・心理・社会モデルは学科の全学生が学ぶ内容として位置付けている。 - 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士を目指す学生に対して、「人と環境の相互作用」に関する知識と技術を習得する科目群、社会状況や実践を通して得られた情報を基に説得力を持った解決法を提案する力を養う科目群、人々の福祉に貢献できる実践的な力を習得するための科目群を配置する。
- 公認心理師や心理学の基礎資格である認定心理士を目指す学生に対して、人間の「心と行動」に関する知識と技術を習得する科目群、人間の「心と行動」および社会を把握するための実践的方法論を学ぶ科目群、人々の心の健康の保持増進に貢献できる実践的な力を習得するための科目群を配置する。
- 第2項、第3項の科目群には学生の興味関心に応じて相互に受講可能な科目を設定しており、社会福祉学と心理学の両方を学ぶことができるように編成している。また、これらの科目群を通して得られる知識と技術は対人援助場面に限らず広く地域社会に役立てることが可能であり、その土台となる円滑な人間関係を展開する力を養う科目群を設ける。
地域包括支援学科
【教育課程の編成】
地域包括支援学科は、学位授与方針(ディプロマポリシー)を達成するために「ソーシャルワークコース」「心理学・カウンセリングコース」「地域包括ケアコース」を設け、4年間のカリキュラムを「基礎科目」、「基幹科目」、及び「応用科目」の3つの科目群によって構成します。
【教育内容・方法等】
「基礎科目」は、人間の人格性を基盤とする学部共通の教養教育として、幅広い視野と豊かな人間性を培うため、基礎科目として開設された一連の科目群(「導入・開発」「基礎教養」「言語文化・コミュニケーション」「情報・文献」「スポーツ・保健」「現代教養」)より修得すべき単位を定め、主体的に学ぶ力を習得します。授業は、講義または演習形式で行います。
「基幹科目」は、「ソーシャルワークコース」「心理学・カウンセリングコース」「地域包括ケアコース」で異なっており、各コースには、専門資格の取得を可能にするための諸科目を配置します。また、学生の力を醸成するため、各コースに「必修科目」を設置し、次の①から⑤までの科目間の連動性を視野に入れて教育課程を編成します。授業は、講義または演習形式で行います。
- 社会福祉士・公認心理師・精神保健福祉士・介護福祉士の国家資格取得(国家試験受験資格の取得を含む)に必要な専門科目
- 分野別のソーシャルワーク系科目や心理学系科目、及び教育系科目、その他の専門科目
- 医療・福祉・心理・教育分野等における質の高い実践力を習得するために編成された少人数制による実習系科目
- 具体的な援助場面を想定した実技指導を通して、質の高い実践力を1年次から段階的に習得するために編成された少人数制による演習系科目
- 人間の心と行動や地域社会の特徴を科学的に研究する技術や態度を形成するために編成された、実験系科目並びに研究法に関する科目
「応用科目」では、学生自身が、人間の心と行動、また、地域社会や福祉に関する課題を設定し、適切な実験・調査等によって課題の解決を図り、これを「卒業論文」として報告するまでの過程を支援する少人数のゼミナールである「専攻演習Ⅰa」「専攻演習Ⅰb」「専攻演習Ⅱa」「専攻演習Ⅱb」を設置しています。
こども教育保育学科
【教育課程の編成】
本学科は、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)で示された、教育、保育、児童福祉に係る専門的知識・技能を備え、豊かな人間性をもった人材養成を実現するために、4年間のカリキュラムを「基礎科目」「基幹科目」「応用科目」の3つの科目群によって構成する。
【教育内容・方法等】
「基礎科目」は、人間の人格性を基盤とする学部共通の教養教育として、幅広い視野と豊かな人間性を培うため、基礎科目として開設された一連の科目群より修得すべき単位を定め、主体的に学ぶ力を習得する。
「基幹科目」は、教育・保育に係る理論的探究力と実践力の両者を培う目的から構造化された、次の7つの領域から編成しており、授業は、それぞれの科目の目的に沿った形で、講義または演習形式で行う。
- 自己教育力(学ぶ力)を育む科目群
- 教育・保育・福祉の意義とこどもの基本的理解を学ぶ科目群
- 教育・保育に関わる専門的知識を学ぶ科目群
- 教育・保育に関わる専門的技能を学ぶ科目群
- 教育・保育に関わる指導法を学ぶ科目群
- 教育・保育に関わる援助技術を学ぶ科目群
- 教育・保育実践に関する科目群
なお、乳幼児期からの一貫した人間形成に関する広い視野を育成するため、基幹科目のうち、教育・保育の基礎や子どもの発達等を扱う特に重要な科目(「保育原理」「教育の基礎理論」「子どもと宗教」「子ども家庭福祉」「発達と学習の心理学Ⅰ」「総合演習」)は、全学生における卒業要件科目とする。
「応用科目」は、「専攻演習Ⅰa」「専攻演習Ⅰb」「専攻演習Ⅱa」「専攻演習Ⅱb」と、その成果である「卒業論文」によって構成される。また、教育・保育・児童福祉に係る理論的探究力、実践力を学生自身の主体的な学びから培うことができるように、「卒業論文」として(1)理論研究、(2)製作研究、(3)実技研究の3つのジャンルを設けている。
大学院
本研究科では、学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に示した能力を取得させるため、次のような体系的な教育課程を編成し、身につけるべき力を定めています。
【博士前期課程】
- 博士前期課程には、統合科目、基軸科目、展開科目からなるカリキュラムが設定されています。
- 本課程では、統合科目を履修し、また、他分野の基軸科目を履修することが可能であり、それによって多角的思考力や分析力を身につけます。
- 本課程では、専門分野の基軸科目、展開科目を履修することによって専門分野における問題解決力、専門職としての実践力を身につけます。
【博士後期課程】
- 博士後期課程には基盤科目、総合展開科目からなるカリキュラムが設定されています。
- 本課程では、基盤科目の履修により、十分な学術専門知識および新たな知を創造する能力を身につけます。
- 本課程では、統合展開科目により各研究分野で学術的な成果を上げるための実行力を身につけます。
アセスメント・ポリシー (学修成果の評価)
【博士前期課程】
学修成果に対する評価は、以下の3点を総合的に評価します。
- 履修した授業科目の成績
- 提出される学位請求論文に係る研究発表
- 学位請求論文
【博士後期課程】
学修成果に対する評価は、以下の3点を総合的に評価します。
- 履修した授業科目の成績
- 提出される学位請求論文に係る学内外での研究発表
- 学位請求論文